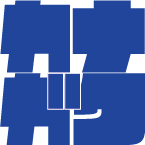『いのちは贈りもの ホロコーストを生きのびて』の読書感想文です。
分量は、題名・学校名・氏名を除き、400字詰め原稿用紙で5枚ちょうどです。
目次
いのちは贈りもの ホロコーストを生きのびて
広告
『いのちは贈りもの ホロコーストを生きのびて』を読んで
神奈川 太郎
私は『いのちは贈りもの ホロコーストを生きのびて』を、あまりおもしろく読むことができなかった。
意図は分かるつもりだ。この本が書かれた意図も、この本が推薦された意図も。
この本が書かれた意図は、「記録」だろう。どうしようもない暴力を前にして唯一できる抵抗としての「記録」だろう。暴力が襲い掛かってきたとき、そしてそこから逃げることすらできないとき、私たちにできることは「記録」することだけだ。克明にすべてを記録し、正義を信じて報われるのを待つ……。
記録は詳細であればあるほど良い。細かさがリアリティを生み、リアリティが真実味を与える。『いのちは贈りもの』の描写が嘘だと思われることは少ないだろう。その描写からは、事態が日に日に悪化していく様子が目に見えるように分かる。
この本が推薦された意図は、「訳者あとがき」に衒いのない文章で書かれている。
「世界のあちこちで排外的な動きが強まり、テロも絶えない現在、差別や対立や戦争、人としてのありかた、そして平和の尊さについて、本書を通し」
あらためて考えることが望まれている。
この本は決してエンターテイメントではない。読んでいて胸がすくものでもない。しかし、おもしろいかおもしろくないかに関わらず、また、エンターテイメント性の有無に関わらず、読むべき本というものがあるのだろう。そしてきっと、この『いのちは贈りもの』のような本こそ、そういった本の一冊なのだろう。
しかしそれでも、私は、「どうでもいい」と思ってしまった。私が想像するふたつの意図、つまり、この本が書かれた意図と、この本が推薦された意図とに沿って、読書をすることができなかった。
まず、三〇〇ページを超える分量に辟易してしまった。途中で飽きてしまった。「この種の本」の常として、どうせ「悲惨でした」の変奏曲が続くだけだろうと思えてしまった。単一の旋律で三〇〇ページを読むと思うと、気持ちが滅入った。
描写も、私には、あまりにも細かすぎた。クリストフが嘘をついているとは思わないから、些細なことまで細かく書くのはやめてほしい。歴史学者であれば、そういった細部にも目がいくのだろう。しかし私は一般書を読む一般の読者だ。
文章の書かれ方も私には合わなかった。『いのちは贈りもの』は始終、短い文章の連続で構成されている。段落もひとつひとつが短く、章立ても細かい。それらが私に、どこか散漫な印象を与えた。唯一の糸として記述をつなぐのは、時系列だけだ。こうした形で書かれた本としては、三〇〇ページはあまりに長過ぎた。
じっくり読めば、もっと興味深かったのかもしれない。しかし、じっくり読もうとする気もあまり起きなかった。そうするには時間が惜しかった。
読み手として、受け手として、私に問題があったことは明らかだ。
『いのちは贈りもの』のような、ユダヤ人への差別と虐殺の物語が薦められたとき、わたしはつい思ってしまうのだ。
「そんなことは今の私にとってどうでもいい」
そういう本を薦める方々に、つい思ってしまうのだ。
「反戦や平等を説く前に、まず目の前の私を助けてください! いつもいつも同じような本を薦めるのはやめてください。この私を救う物語をください!」
こう思ってしまうのは、たぶん、私自身に余裕がないからだろう。
平和や平等が語られる度に、わたしはどこか空々しさを感じ取ってしまう。
「そう語るあなたたちは、目の前のひとりひとりにどれだけ寄り添ってくれるのですか」
ユダヤ人差別に限らず、黒人差別や性的少数者への差別など、さまざまな差別の解消に取り組んでいる方々がいる。また、平和運動に取り組んでいる方々も多い。それはそれで結構なことだ。間違いなく。
しかし、もしそうした方々が、目の前の貧しさに喘ぐ隣人を差し置いて「活動」に取り組んでいらっしゃるのであれば、喘いでいる側からの反感を買うのは必至だろう。少なくとも私は、反感を抱いてしまう。
私たちは貧しくなった。博愛主義を掲げられる余裕がない程に。それにも関わらず、隣人に手を差し伸べずに、遠い国でかつて苦しんだ他人への想像力や、そうした他人の経験からの学びを要求するのは、筋違いであるように思えてしまう。私のなかの「排外的な動き」の根だろう。
きっと私は、時代が時代ならば、小さな少女をこん棒で殴る側に立っていたに違いない。