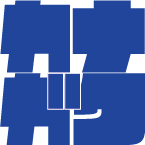2016年度「第62回 青少年読書感想文全国コンクール」の課題図書、『ハーレムの闘う本屋 :ルイス・ミショーの生涯』の読書感想文例です。
分量は、400字詰め原稿用紙で5枚ぴったりです。
ハーレムの闘う本屋 :ルイス・ミショーの生涯
広告
『ハーレムの闘う本屋 :ルイス・ミショーの生涯』を読んで
神奈川 太郎
私たちは皆、幸福を求めて生きている。幸福を得るために必要なのは、自己の欲求の充足だ。
自己の欲求を満たす道は二つある。
ひとつは、欲求のレベルを下げる道だ。仏教的なアプローチと言えるかも知れない。人間の不幸は膨れ上がっていく欲望を満たせなくなることから生まれるのだから、そもそも欲しないことを目指そうというものだ。
もうひとつは、欲求をあくまでも満たしつづけようとする道だ。これはなかなか険しいアプローチである。なぜなら、ある欲求が満たされると、さらに大きな別の欲求が頭をもたげるからだ。
現代社会に生きる私たちは、特に大人に近づいていくにつれて、前者の道をとることが多くなっていくのではないだろうか。大それた夢や希望など、叶うはずもないのだ。私たち自身のこれまでの在り方が、それを証明している。そうであるならば、身の丈に合った欲求を抱き、ささやかなことに幸せを感じて生きていきたいと思う。
近年の地球環境問題なども、この考え方を後押しするように思われる。ただひたすらに成長と発展、豊かさを追い求め続けてきた人類は、自分たちの行為によってその生存を脅かされてきている。もう外面的な豊かさに固執するのはやめにする時だ。内面的な、心の豊かさを追い求めようではないか……。
ルイス・ミショーがもしこう言われたら、どう言い返すだろうか。きっとこう言うに違いない。
「それなら、家にかえってその上等の服をぬぎ、エプロンをかけてほうきをもってこい。」
と。社会の構造に守られた大上段から、何を偉そうに、と。
ルイスは本当に、生涯「闘う本屋」であり続けた。最後まで、決して諦めることをしなかった。
彼も、そして彼と同じミショー家の血が流れるこの本の作者も、人の心を煽るのがうまい。本を読み終えた後に私の心に残ったのは、闘争心の炎だった。彼の言葉と生き様を前にすると、闘わない生き方がひどく卑怯な生き方に思えてくる。
「しかしお前はいったい何と闘うというのか。闘うべき相手などどこにもいないではないか」
そう問われるかもしれない。しかし、それなら私は逆に問い返そう。
「では、あなた方の生きる世界は、何不自由のない『水晶の階段』なのか」
と。
私たちの生きる世界は、決して満たされた世界ではない。特に、私たちの生きる「社会」はあまりにも不完全だ。この社会は皆が自由な社会だろうか。公正な社会だろうか。いつもどこでも正義が行われている社会だろうか。絶対にそんなことはないはずだ。
力を持つ者に屈する者たちがいることだろう。不平等に喘ぐ者たちがいることだろう。そして、正義を信じて裏切られた者たちがいることだろう。
私たちは幼い頃、もっとこうしたことに敏感だったはずだ。それがいつの間にか、自分たちが上っている階段に浮き出た鋲にも、はがれた絨毯やむきだしの床にも、目をつぶるようになってしまった。
世界の不完全さに目をつぶるのは、自分さえ良ければ構わないというエゴイズムの為せる業だ。なぜなら、不完全さはいつも、弱いものから餌食にしていくからだ。
ルイス・ミショーにも選択肢があった。闘わないという選択肢が。「いわゆるニグロ」として、差別を甘受して生きる道もあったはずなのだ。しかし、彼はその道を歩まなかった。あくまで闘うことを選び、その結果として多くの黒人たちを差別から救った。
私たちには、自分たちが生きるこの社会をより良いものにしていく倫理的な義務がある。本当に弱い者は、闘うことすらできないからだ。私たちが闘い、彼らを救わなければならない。
どう闘うのか。知ることによって、だ。闘うためには、強くならなければならない。強くなるためには、知識を身に付けることだ。暴力によって闘うのは分が悪い。なぜなら、暴力で闘った場合、大抵は相手の方が強いからだ。警官につぶされたルイスの片目が物語っている。闘うなら、知略を尽くして戦うべきだ。その正しさは、現代アメリカにおける黒人の地位の向上が饒舌に物語っている。
「わたしの人生は水晶の階段じゃなかったけれど」それはそれで幸せです――などと言う気は微塵もない。
「引き返してはいけない。/ちょっとつらいからといって/腰をおろしてはいけない。/ここで倒れてはいけない――/わたしだってまだ足を止めていないのだから、/上りつづけているのだから。」