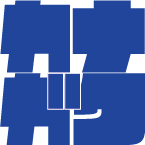神奈川県内△△中学校の 2019 年度 2年生 定期試験 国語で出題された「バイオロギングの可能性」の問題と解答です。
広告
目次
問題
問一
波線部ア~ウの漢字の読み方をひらがなで答えなさい。(各一点、計三点)
〔ア 亀裂/イ 豊富/ウ 費〔やす〕〕
問二
①波線部とありますが、これはなぜだと筆者は考えましたか。次から―つ選び記号で答えなさい。(二点)
- ア 深く潜るよりも浅い潜水を繰り返すほうが効率がよいから。
- イ 浅く短い潜水を数時間おきに行うと多くの餌を捕れるから。
- ウ 長時間潜ると休む時間が短くなり、何回も潜水できるから。
- エ 海の深いところはライバルが多く、深く潜っても餌が少ないから。
- エ ペンギンにも得意不得意があり、深く長く泳げないペンギンもいるから。
問三
②波線部とありますが、ペンギンたちがこのような行動をとるのはなぜだと筆者は考えましたか。本文から十一字で抜き出しなさい。(二点)
問四
③波線部とありますが、次のような工夫をしているのは、何ペンギンですか。エンペラーペンギンならエ、アデリーペンギンならア、どちらのペンギンでもなければ×を解答らんに書きなさい。(二点)
捕食者から身を守るために、短い潜水を数多く繰り返し、潜水の開始と終了時間を一致させている。
問五
野生のペンギンに比べて、水族館のペンギンが暮らしている様子を表現した言葉を本文から四字で抜き出しなさい。(二点)
問六
筆者の考えと一致するものを次から―つ選び記号で答えなさい。(二点)
- ア バイオロギングの研究者たちは、なるべく失敗しないように自然環境での調査を避けることで、手法の改良を重ねてきた。
- イ バイオロギングによる調査で大切なのは、水中よりも人間の行動圏である陸上の動物が記録する情報である。
- ウ バイオロギングで得られたデータを活用すれば、人間は地球上のより広い範囲を自由に移動できるようになる。
- エ バイオロギングによって動物が記録する情報は、これまでの人間の知識や経験を越え、私たちの視野を広げてくれる。
- オ バイオロギングは大胆な発想から生まれたので、これからは常識にとらわれすぎずに、様々なことにチャレンジしていくべきだ。
広告
解答〔学校発表〕
問一
ア きれつ
イ ほうふ
ウ つい
問二
ア
問三
捕食者から身を守るため
問四
×
問五
のんびり
問六
エ
参考
光村図書,「著者からの言葉」,https://www.mitsumura-tosho.co.jp/material/pdf/kyokasho/c_kokugo/material/kohoshi_c_kokugo_8005.pdf ,2019 年6月 22 日.